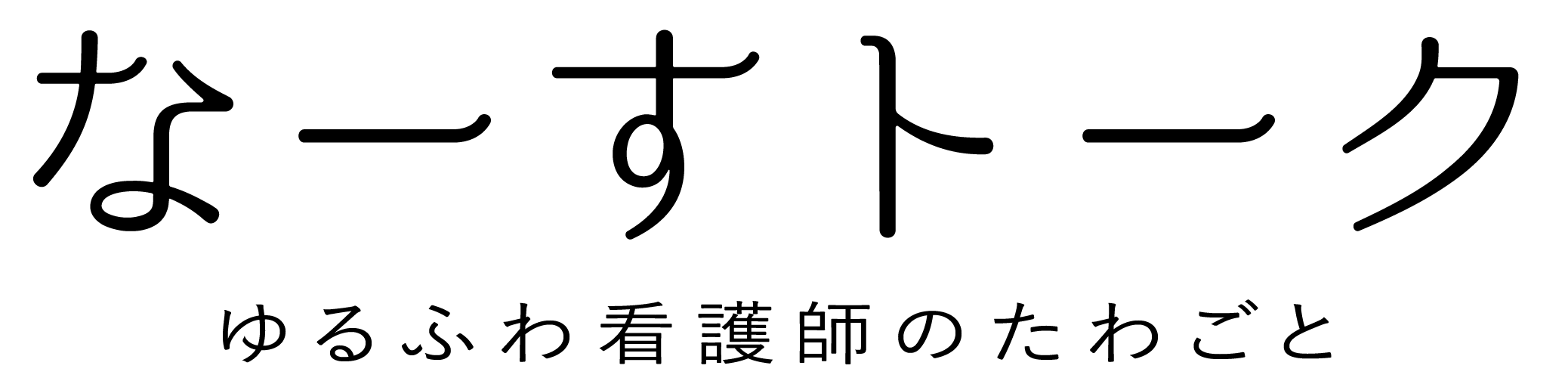患者さんが亡くなるという場面に立ち会ったことのある看護学生もいるかと思います。人が亡くなってしまうということを目の当たりにしたとき、色々と考えさせられます。「私がしてきたことってなんだったんだろう」と思う人もいるかもしれません。しかし、看護は決して無駄ではありません。
とある病棟で体験したことを例に、看護の大切さを紹介します。
こんな患者さんがいました
私が出会った患者さんは、急に体調を崩して入院した50代の男性Aさんです。
奥さんに連れられて入院しましたが、がんであることがわかりました。
入院したときには、すでに体のいたるところにがんが転移していましたが、色々な検査をしても、どこからがんが発生したかはわかりません。そのため、医師が選択したのは、がんによる症状を軽くするための抗がん剤の使用でした。
口数は少ないAさんでしたが、笑顔で看護師に接してくれました。けれど、Aさんの性格やがんが脳まで転移していたこともあり、自分の心情や不安を語る場面はほとんどありませんでした。
治療を続けていくうちに、Aさんの髪は抜け落ち、素敵な笑顔も段々と弱弱しくなっていきました。それを見ていた奥さんは、その先に起こりうることを考えては涙することもあり、看護師はそんな二人を看護や話の傾聴といったかたちで支えることに徹底しました。
Aさんに対しては、Aさんが少しでも楽になるように、Aさんの体調に合わせて薬剤を投与したり、むくんでしまった足は奥さんと一緒にマッサージを行いました。
自分からは思いを表出することはありませんでしたが、看護師から「つらいですよね。いつでも伺いますよ」などと声をかけることは怠りません。奥さんに対しては、つらいときにはそばに寄り添い、話を聞いて不安な気持ちを少しでも軽減できるように関わりました。
亡くなってからわかること、気づくこと

結局Aさんは、入院して数週間で亡くなりました。医療としては原発巣を発見できず、治療も十分だったか疑問に残ってしまい、しこりが残るかたちでした。しかし、最後の奥さんの言葉が希望をくれます。
奥さんは「ここに入院して本当に良かったです。みなさんの懸命な気持ちが私たちの心を癒してくれました。主人もそういっているようです」と触れたAさんの頬には、安らかで、ほんのり笑みがみられました。
その後、亡くなってから解剖を行い原発巣がわかりました。看護師は、全員でカンファレンスを開き、そのかかわりを振り返ります。
看護は助けるだけが目的ではない
医療は生命を救うためにありますが、それだけではありません。特に看護においてはその人がその人らしく生きるために手助けできることがたくさんあります。
このように患者さんが亡くなる結果となっても、その人の人生に寄り添い、少しでも楽にその人らしく過ごせるようにお手伝いすることができる看護は、決して無駄ではないのです。